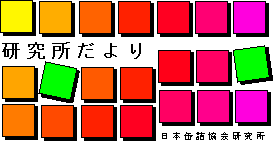 (缶詰時報'98年9月号掲載)
(缶詰時報'98年9月号掲載)昔の化学分析方法をみますと、問題のシアン化カリや亜ヒ酸塩をはじめとした微量で致死に至る薬品、例えば水銀や鉛などの金属塩や溶媒など、かなりの頻度で使用されています。その量も比較的多く、また高濃度が使われています。先人が当時として特異的であり鋭敏で、精度良く目的物を定性、定量できる薬品という観点からのみ採用したのでしょうが、毒性はあまり考慮されていません。今では同じ方法は採用しませんが、その薬品を別のものに変えてやることはあります。こうした薬品は今とは比べものにならないほど無頓着に購入、保管、使用し、廃棄していたものと思います。
機器分析が主体となった現在では、毒性の強い薬品はほとんど使いません。例え使ったとしても数十分のⅠ程度の量と濃度ですみます。
当所にも問題の前記の薬品を含め強い毒性のある薬品は使わないのに持っておりました。毒性の強い薬品、長期間使われていないもの、今後使わないと予想される薬品は毎年少しずつ廃棄処理をしていましたが、先の引っ越しの際に一括廃棄しました。大変な数があり、廃棄処理費用もかさみましたが(薬品によっては購入費の3倍程度)、長年捨てられず、管理・保管への気遣いばかりの薬品が少なくなりほっとしています。
現在、ほとんどの薬品は1週間程度あれば納品されますので、毒性などが懸念される薬品はもちろん、定常的に使う薬品もできるだけ必要最少量を使うたびに購入し、在庫しないようにしています。個々の購入費は少し高いのですが、有効期限、保管・管理面や廃棄処理費用を考えると結果的に安いと思っております。
(研究所次長兼第一研究室長 鈴木 健次郎)
試験・研究・調査
その他